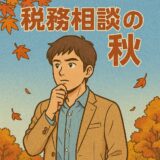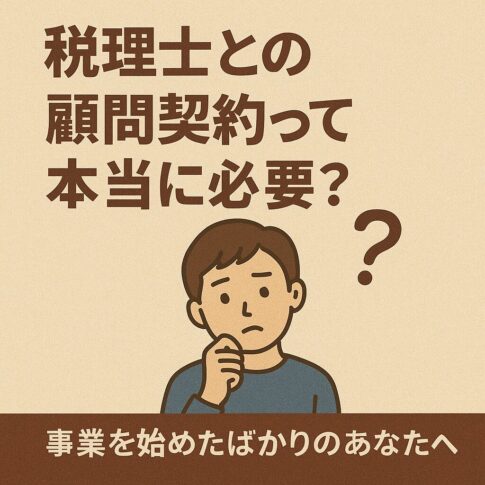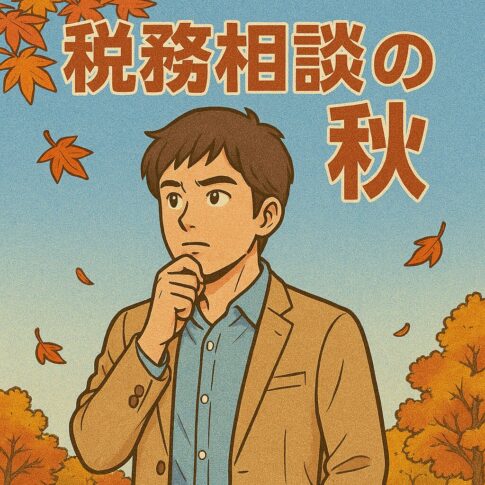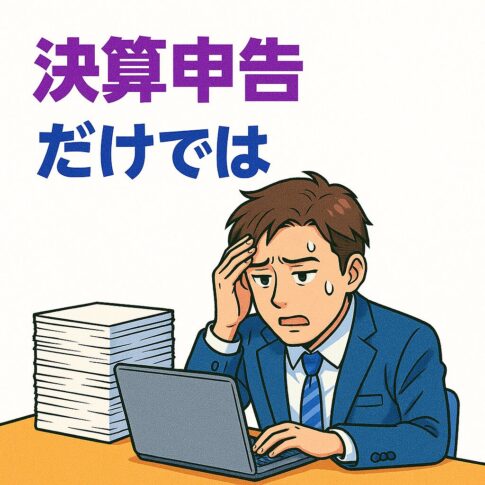経営をしていると、「今月は利益が出たはずなのに、なぜか口座にはお金が残っていない…」という場面に直面することがあります。
これは珍しいことではなく、実際に、多くの中小企業の経営者が同じ悩みを抱えています。
その原因は、「損益と資金繰りの不一致」によるものです。
では、なぜこのズレが生まれるのでしょうか?
主な理由を分かりやすく整理して解説します。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
売上は計上されても、現金はまだ入っていない(売掛金)
損益計算書では、売上は「商品やサービスを提供した時点」で計上されます。
しかし、実際の入金は1ヶ月後や2ヶ月後になることも珍しくありません。
建設業などでよくあるのが、末締め請求の翌月末払いなどです。
この場合、売上から入金までに、少なくとも1ヶ月以上はタイムラグがあります。
つまり、帳簿上は儲かっていても、現金が手元に入っていない状態が生まれます。
売掛金が多い月ほど、このギャップは大きくなります。
仕入や経費はすぐに支払う(買掛金・前払い)
一方で、仕入れ先や外注先への支払いは現金で即時に行うケースもあります。
損益計算書上では「費用」として計上されているだけですが、実際には先にお金が出ていくのです。
特に前払いの経費や支払いサイトが短い取引先が多い場合、資金繰りに与える影響は大きくなります。
スポンサーリンク
減価償却費は「費用」だが現金は出ていない
損益計算書には「減価償却費」が含まれています。
減価償却費は、設備や車両などの資産を何年にもわたって分割して費用化するものです。
支払い方法が一括であっても、分割であっても、減価償却費の計算は変わりません。
ですので、利益とお金の増減は一致しないこととなります。
また、支払金額よりも減価償却費のほうが先に計上されることもあります。
つまり、「利益が減っていても現金は減っていない」状態もありえます。
借入金の返済元本は損益に影響しない
銀行などからの借入金の返済についても注意が必要です。
損益計算書に反映されるのは利息だけで、元本の返済は費用として計上されません。
借りた金額をそのままプールしているのであれば、資金繰りにそれほど影響はないのですが、一般的には借入金を原資として、先行投資することが多いので、返済分は利益から捻出する必要があります。
そのため、「利益は出ているのに、借入返済で資金が苦しい」という現象が起こります。
税金や社会保険料の支払いタイミング
利益が出れば、当然ながら法人税や消費税などの支払い義務が生じます。
この支払いは、法人であれば、決算から2ヶ月後等にまとめてやってくるため、資金繰りに突発的な負荷を与えることになります。
なるべく早くから、決算の終着点を予測し、シミュレーションしておくことが大切です。
利益と資金繰りは「別モノ」として考える
損益と資金繰りは似て非なるものです。
利益が出ていても、現金が足りなければ企業は回りません。
逆に言えば、資金繰りさえ安定していれば、赤字でも事業は続けられるのです。
経営者にとって重要なのは、「利益」だけを見るのではなく、キャッシュフローを常に意識することです。
資金繰表をつける、売掛金と買掛金のバランスを取る、資金繰り予測を立てる、場合によっては前もって借り入れをする等・・・。
こうした地味な管理ができるかどうかが、企業が生き残れるかどうかの鍵になります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク